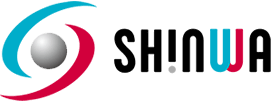消防設備点検コラム

【教えて】火災報知器について詳しく知りたい!
2025年2月17日
本記事はこんな方におすすめです
- 消防設備士として専門知識を深めたい方
- 商業施設や工場、オフィスビルなどの防火管理者・防災管理者・担当者
- マンション管理組合の理事になったので予備知識がほしい方
- 住宅リフォームを検討しているので火災報知器の知識を深めたい方
- 家が古くて火災報知器が付いてないので設置したい方
全国の火災報知器ファンの皆さま、大変お待たせしました。
「火災報知器についてもっと詳しく知りたい!」という皆さまからの熱い声にお応えして、今回は火災報知器について詳しくお話していきます!
火災報知器は万が一火災が発生した際の被害を最小化して人命を守るために欠かすことのできない非常に大事な設備です。今回は住宅用だけでなく業務用の火災報知器についてもお話していきます。商業施設や工場、オフィスビルなどの防火管理者や防災管理者、担当者の方など、業務上必要な知識を深めたい方も是非お読みください!
それでは早速いきましょう。
火災報知器の分類

皆さんは火災報知器と聞いて何を思い浮かべますか?
恐らく、マンションやオフィスの廊下に設置されている非常ベルと赤い円形ライト付近に設置されている押しボタンのアレや、オフィス・自宅寝室・キッチンの天井などに設置されている丸いアレではないでしょうか。皆さん一度は目にしたことがあると思います。
実は、火災報知器は住宅用の「住宅用火災警報器」と業務用の「自動火災報知設備」 の2つに大きく分類することができます。
住宅用火災警報器は家庭内の人命保護を目的としてシンプルに設計されていますが、自動火災報知設備は、不特定多数の人を守るための高度なシステムとして構成され法令で厳しく管理されています。
住宅用の「住宅用火災警報器」も業務用の「自動火災報知設備」も設置する目的は人命や財産を守ることですので、それぞれの用途や建物の特性に応じて正しく設置することが非常に重要です。
まずは、住宅用の「住宅用火災警報器」と業務用の「自動火災報知設備」の目的や特長などを詳しく比較して確認していきましょう。
| 住宅用火災警報器 | 自動火災報知設備 | |
|---|---|---|
| 対象 | 戸建て、マンション、アパートなど小規模な一般家庭 | マンションやオフィス、ホテル、民泊、商業施設、工場、病院、学校など多数の人が利用する施設・場所 |
| 目的 | 主に家庭内の人命を守るため | 施設利用者が迅速に避難できるようにするため |
| 住宅用火災警報器 | 自動火災報知設備 | |
|---|---|---|
| 設置場所 | 寝室、階段、リビング、キッチンなどの天井または壁の高い位置 | 建物内のすべての部屋、廊下、階段、エレベーター周辺、避難通路などの天井面や壁面 |
| 設置基準 | 自治体の条例に基づき設置 | 消防法施行令第21条に基づいて建物の用途、規模に応じて設置 |
| 主な構成 | 住宅用火災警報器、移報中継アダプタなど | 受信機・感知器・ベル・発信機・表示灯・スピーカーなど |
| 通知方法 | 住宅用火災警報器内蔵の音声警報やブザーで住人に直接通知(スマートフォンに通知する無線通信対応のものもあり) | ベルの鳴動やスピーカーからの音響警報で建物内外の人に通知 |
| 住宅用火災警報器 | 自動火災報知設備 | |
|---|---|---|
| 点検頻度 | 年に1回程度の自主点検 | 6か月に1回以上の定期点検(消防法で義務付) |
| 点検方法 | テストボタンを押して動作確認 | 専門業者による機器の動作確認、受信機の表示確認、配線のチェックなどの総合点検を実施(消防署への報告義務あり) |
住宅用は直接住民に通知して住民の人命を守る、業務用は建物内外の不特定多数の人に通知して迅速な非難を促す、という特長がありました。
次は火災報知器が火災を感知する主な3つの方式について確認していきましょう。
感知器の3つの感知方式

感知器には主に「煙感知器」「熱感知器」「炎感知器」の3つの感知方式があり、火災を迅速に感知するために、それぞれ異なる原理と技術が使用されています。
感知器の設置する場所の用途や取付面の高さによって設置できる感知器の種類が決まっており、煙、熱、炎の複数の感知方式を建物全体で組み合わせることで、火災をより早く正確に検出することができます。なお、二つの異なった感知方式を組み合わせた複合式感知器もあります。
煙感知器
煙感知器には大きく分けて光電式とイオン式の2つの方式があります。いずれも火災時に発生する煙を感知するタイプの感知器で、周囲の空気が一定濃度以上の煙を含むに至った際に作動します。主に廊下、通路、階段、居室や、特に煙の滞留しやすい無窓階や地下階、11階以上の階に設置します。また、住宅用火災警報器にも多く採用されており、主にリビング、寝室、廊下などに設置されます。ただし、キッチンや浴室など湿気や蒸気が多く発生する場所は誤作動の恐れがあるため不向きです。
光電式煙感知器

光電式煙感知器は、煙が発生した場合に、内部のLEDライトが煙の粒子に反射して散乱光を検出する仕組みです。この光をセンサーが受け取ると、煙があると判断して警報を発します。温度の変化にあまり影響されませんが、蒸気や煙草の煙などにも反応する場合があり誤動作のリスクがあります。
イオン式煙感知器
イオン式煙感知器は、放射線を使って空気中の粒子に電荷を与え、煙の粒子がその電荷を変化させることで煙の存在を感知する仕組みです。敏感に煙を感知するので火災の初期段階で警報を発することができます。放射線を使っているため設置や廃棄の際に特別な処理が必要です。
熱感知器
熱感知器は、火災時に発生する温度の上昇を感知するタイプの火災報知器で大きく分けて定温式と差動式の2つの方式があります。火災によって周囲の温度が急激に上昇するのを感知し、その温度変化をセンサーが捉えて警報を発します。蒸気、煙、粉塵が発生する恐れのあるキッチン・厨房や浴室、ボイラー室、駐車場など煙感知器が誤作動しやすい場所に使用されることが多いのが特長です。
定温式熱感知器

定温式熱感知器は、設定された一定温度に達すると作動します。一般的には60℃~150℃の範囲で温度設定されており、火災が発生してその温度に到達すると作動します。ただし、急激な火災や小規模な火災には反応が遅れる場合があります。
差動式熱感知器

差動式熱感知器は、周囲の温度と急激な温度変化を感知して火災を検出します。定温式に比べて温度差に反応するため、火災の初期段階や規模の小さい火災でも反応しやすいのが特長です。ただし、温度変化が緩やかな火災に反応しにくい場合があるので注意が必要です。
炎感知器
炎感知器は、火災時に発生する炎から放射される赤外線や紫外線を感知して作動します。大型の工場や化学プラントなど爆発や引火の危険が高い施設に設置されます。
赤外線感知器

炎が発する赤外線の波長を捉えて火災を検出します。特に高温の炎を感知する能力があります。炎から発せられる熱と光に反応し、煙の少ない小さな火災も早期に感知できます。ただし、煙や他の熱源に影響されることがあるため設置場所に注意が必要です。
紫外線感知器
主に工場などの高温環境に設置される紫外線感知器は火災時に発生する紫外線波長を捉えて火災を検出します。火炎の直接的で迅速な検出が可能ですが、紫外線は周囲の環境や光源によって影響を受けるため設置条件は厳しくなります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、火災報知器について詳しくお話しました。
火災報知器は、住宅用の「住宅用火災警報器」と業務用の「自動火災報知設備」 の2つに大きく分類され、感知方法は「煙感知器」「熱感知器」「炎感知器」の3つの方式があります。
それぞれ特性や利点が異なるため設置する施設や場所、条件等に応じて適切な感知方式を選定する必要があります。万が一の火災の早期検知と被害最小化のためにも適切な火災報知器の設置と定期点検・メンテナンスが重要です。
火災報知器の設置・リニューアルをご検討の際は、お気軽に当社までご相談ください。